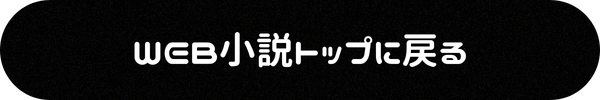本当に動物みたいだなと思って、荒く息をつきながら、真実は笑った。
(最短記録かな)
同じ家で暮らしていた頃、両親の目を盗んで何度もこんな行為に耽った。暴力に等しいやり方で、裕司の衝動のままに体を曝かれたこともある。床に突き飛ばされて服を剥ぎ取られて犯されるまであっという間で、惨めさに泣きじゃくったこともあるが――その時よりも、この夜の方がよっぽど体を繋ぐまでの時間が短かった。
まだ、真実の体の中には弟の熱がある。裕司は達する寸前に身を引こうとしたのに、真実は相手の体に脚を絡めてそれを阻んだ。後が大変なのは経験上知っていたが、一瞬でも離れたくなくて必死だった。
裕司も真実の上で呼吸を乱している。すべての体重を遠慮なく預けられ、真実にはその重さと息苦しさが心地好くて気が遠くなりそうだ。
「何、笑ってんの」
たった一晩の逢瀬のために長い時間をかけて、はるばるこんな部屋までやってきたくせに、裕司の口調はぶっきらぼうだ。それが妙に嬉しくて、真実はかすかに汗に濡れた弟の髪を優しく撫でた。
「話したいことがたくさんあったのに、全部吹き飛んだなと思って」
「……聞くけど?」
裕司の返事に、真実は首を振った。
「全部並べてたら終わらないよ。最初にここに来た日のことから、今日まで、全部だから。俺のことも……裕司がどうしてたのかなってことも」
「別に今までと何も変わらない」
相変わらず、裕司の口調は素っ気ない。
「ただ、真実がいないってだけ」
なのにその声音から裕司の餓えが伝わってきて、真実は苦しくなった。
裕司の心情を想像する必要はない。きっと真実と同じくらい、時々は気が変になるんじゃないかと思うくらい、寂しかった「だけ」。
(どれだけ言葉を連ねたって足りるわけがない)
捥ぎ取られた時間が恨めしい。今をこらえれば、ずっと弟と一緒にいられる日が来るからと自分に言い聞かせて過ごしてきたけれど、目の前にその姿があって、触れ合って、繋がってしまえば、再び離れる時の苦痛に耐えられるのか、怖くなった。
だから、もっと、もう少しだけでも。
「裕司、もういっかい……」
「……ん」
弟のすべてを体に刻みたい。言葉なんて今は意味がないと思った。どうせ気持ちには及ばない。熱情にも、欲望にも足りない。
「っ、裕司……」
真実の中で、ほとんど固さを失っていなかった弟のものが、ゆっくりと動き出す。
裕司も、ほんの少しだけでも真実の感触を忘れたくないという仕種で触れてくる。
(朝なんて来なければいいのに)
今は互いに与え合う快楽と愛しさ以外、何も感じたくない。
真実は進んで思考を手放して、ただ掠れた声で弟の名前を何度も呼び、相手の呼ぶ自分の名前を何度も聞きながら、熱に溺れた。
誰にも言えない夜を、ふたりきりでずっと過ごした。
昼過ぎに起きると部屋の中に裕司の姿はなくて、嘉彦の荷物もすべてが片づいていた。池内のベッドも空だ。
「……はは」
眩しい光が射し込む窓を見遣って、真実は泣き顔で笑った。
いつの間に眠ってしまったのだろう。絶対に裕司を見送ると思っていたのに。
真実ひとりが、部屋の中でぽつんと、いつもの日常の続きのように佇んでいる。
(服、裕司が着せてくれたのかな……まさか、鴫野じゃないよな?)
全然、覚えがない。
――本当に、夢みたいな夜だった。
ただ体に残る鈍い痛みやあちこちに滲む裕司のつけた痕が、夢じゃないとわからせてくれた。
体を起こすのは少し辛かったけれど、真実はどうにか起き上がって、自分の机の抽斗を開けた。
裕司のくれた葉書がそのまま残っている。
葉書を持って、真実は窓辺に近づいた。窓を開けると、少し冷たい秋の空気が部屋の中にも流れ込んでくる。
「……埼玉は、あっちかな」
自分の暮らしていた街のある方へ見当をつけて、真実は両手を組み合わせて握り締めると額に押し宛てた。
――殉教者みたいだと思って。
不意に、嘉彦が言った言葉を思い出した。
思い出しながら、祈る。
(松下、塚本、それから裕司を助けてくれた人たち。みんなに感謝します。あなたたちにたくさんの倖せが訪れますように)
祈ることが何の力になるかなんてわからない。でも祈らずにはいられなかった。
(裕司。ここを出て自由になったらきっと、一緒にいられるから。……ずっと愛してるから)
神様に祈る必要はない。自分たちの気持ちなら自分たちが一番知っている。
「……鴫野は、どっちに行ったんだろ」
詳しい転校先も引っ越し先も、真実は聞かなかった。
きっとこの場所を出たら擦れ違うこともなくなるだろうから。
ここはそういう場所だから。
もうどこにいるか見失ってしまった友達のためにも、真実は祈った。
(――鴫野。君の許にも倖せが訪れますように。辛い思いをどれだけしても、あの人が君を愛してくれますように)
不意にドアの開く音がして振り返ると、池内が真実に一瞥をくれることもなく自分の学習机の前に座り、いつものようにぶつぶつとひとりごとを言いながら勉強を始めていた。
池内にもきっとたくさんの思いや事情があるのだろう。それを肩代わりしてやることも分かち合うことも真実にはできない。ただ、池内のためにも少し祈った。
夢のような夜は終わり、再びこの場所の日常が始まる。
真実は葉書を大切に抽斗にしまい直して、顔を顰めつつ大きく伸びをすると、いつもと変わらぬ休日をすごすために、池内と並んで自分も机に向かうことにした。
– end –