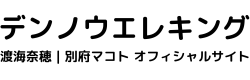今年も大國魂神社の宝物殿で開催されている府中市愛刀会の刀剣展、例年通り中原信夫先生のギャラリートークも行われたので行ってきました。
今年の刀剣展のテーマが「山陽道の刀」だったので、山陽道とはどこをさすのかから始まり、海運、水運についてと流れていき、また興味深いお話がたくさん伺えました。
規模は小さな展示会なんですが、ありがたいことにどんどん来てくれる人が増え、ギャラリートークも予想外の方が訪れて、会の人も神社の人も驚いてました。会長たちが「床は大丈夫か…?(抜けないか?)」という心配をしていたよ。
何となく綿商会館でえらいこっちゃ一般参加者が集った時の同人誌即売会などのことを思い出す私でした。
宝物殿の床は全然大丈夫だそうです。
刀剣展ってもともと足を運ぶのは年配の方が多かったんですが、近年若い女性も増えて、先生的には「何を話したら興味を持ってくれるか?」っていうのを意識しながらのトークだったみたいです。
刀剣会では、「刀の観賞は姿と形から」と言われるように、刀自体の形や刃文、肌などに注目して研究していくんですが、いきなりそれについて話しても戸惑われるかもしれない…ということで、輸送や地理についてからのアプローチで、いろいろ脱線もしつつ、会に行った時とはまたがらっと違うトークを聞けるため、毎年楽しみにしているギャラリートークです。
初めて聞いた! って驚く話もあるんですが、たまに私が「へえ、知らなかった」みたいなことを言うと、先生が「いや僕がいつも言ってるよ」って苦笑するので、私が全然覚えてないだけかもしれませんが。
知りたいことと覚えたいことがありすぎて全然追っつかない。
ギャラリートークとは関係なく、神社所蔵の刀の押し型を取るところも見せていただきました。
大國魂神社の宝物館でも御蛇丸の押し型が飾られていますが、博物館なんかでも押し型を目にした時、ぼんやりと「こうやって取ってるんだろうなあ」と思っていたのと全然違うやり方でびっくりした。
すごく繊細で集中力のいる作業で、傍で見学していても手に汗握る感じでした。
日本刀を直接触るようになる前は、「刀に炭を塗って版画みたいに型を取ってるのかな」とぼんやり思ってたりしました。無知無知。
技術を継承する人がいないようで勿体ない…何かもう職人というより芸術家だなという作業でした。
ただなぞって写し取るだけじゃなくて、三次元のものを二次元に落とし込む知識と技術が必要…。
たまに、ほんとたまにですけど、博物館で展示してある刀と押し型で刃文とか全然違ったりして、何でだろうと思うことがあったんだけど、神技術を目の当たりにして「なるほど…」と深く納得しました。
作業する人によるんだ…。
そして自分がまったく刀を見る目を持ってないな、というのを、押し型に写し出された形や刃文を見て痛感する。押し型を取る前に刀を観賞させていただいたんですが、こう、漫然と眺めてしまって、全然特徴に注目できてないんですよね。「ここが見どころ!」っていうのを一度解説してもらわないと目が開けない。
もっと必要なことを覚えたい。と思い続けて十年経った。十年経っても相変わらず何もわからん。
でも刀の観賞は本当に楽しいし興味深いし、仲間がもっと増えると嬉しいなあ、と思います。
ということで、刀剣展は今月28日まで続くので、お時間ある方はぜひ遊びにいらしてください。
愛刀会の会員さん所蔵の刀を持ち寄っての展示で、本当にすごくいいものがありますし、神社所蔵のご神刀もかっこいいです。ついでに宝物殿の元からの展示物も見られます。
閉館が4時とちょっと早めなのでお気をつけ下さい。
大國魂神社自体がすばらしいところなので、お詣りしたり、お守り買ったりもおすすめですよ。